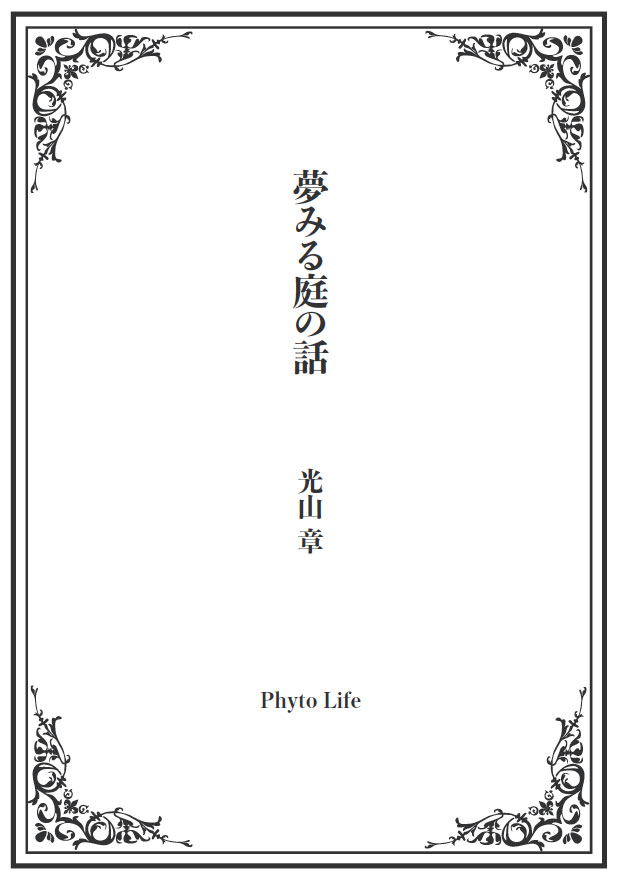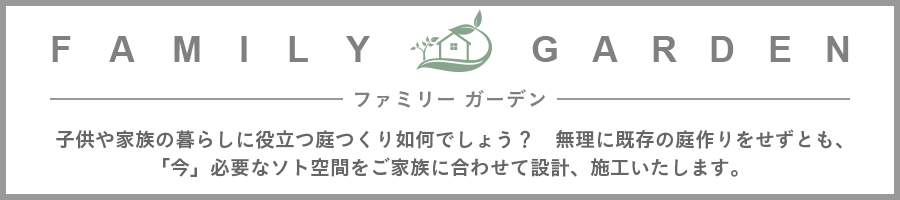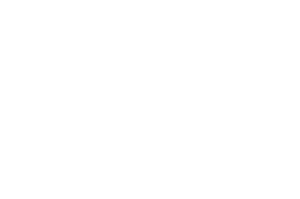夢みる庭の話(前編)
この度、これまで考え続けてきた「庭」或いは「庭の存在意義」の考察をまとめた冊子を発刊いたしました。あくまで現段階でのまとめではありますが、私たちの集大成になったと考えております。ホームページとPDFも併せて公開させていただきますので、お読みいただければ幸いにございます。尚、ホームページでは前編と後半で分けて掲載しております。
庭とは何か
「庭」という言葉がある。この漢字は小さな子供でも知っている言葉であり、私たちは普段使う単語でもある。しかし、改めてその庭とは何かと問われれば、これを明確に答えることは、難しい。
私もまたその答えを即答できない一人だ。しかも、私自身は、実は四十年に渡り、庭仕事をしてきた。多くの庭を手入れし、作庭し、設計してきた。そんな私がこんなことを書けば、一般の人たちは、ガッカリされるだろうし、専門家としての信頼にも傷がつくだろうが、実はそうなのだ。正直言おう。やはり、わからない。
書店をのぞけば、多くの庭に関する書物がある。しかし、その殆どは、庭のスタイルブックと庭に植えるべき植物図鑑に過ぎない。和風、洋風、雑木風などと銘打たれ、さらに純和風、新和風、ナチュラル、モダンなど様々な言葉で庭を定型化している。まるで、庭のカタログ集と言える。また、日本の有名庭園の解説の本や研究書も多く出版されているが、その多くは、有名なその庭を解説するものであり、庭そのものを言及しているものではない。
こうした事実を考えれば、庭とは何かという問題は、考える必要のない問題であったとも言える。私たちは、当然のように誰もが庭の存在に疑問を抱かず、庭は現実「在る」ものとして取り扱われてきたのではないだろうか。私たち庭に携わる人間も、庭の良し悪しは論じても、庭の存在そのものを疑うことなく過ごしてきた。「家庭」という言葉があるではないか。家と庭は一対の存在として暮らしを作っていることを象徴していると思ってみたり、家を建てて庭を持たぬなどと陰口を囁いたりして嘯いてきた。
しかし、仮に一人の偉大な哲学者が、目の前に現れ「では、君たちがせっせと作業し、花を植え、木を植え、石を据え、水を遣るその庭なるものは一体なんなのかね。ひとつご教示願おう」と言われたらどうだろう。
「庭とは、憩いや安らぎを人間に与える場所」だとか、「人が自然に触れる機会と癒しの場」であると答えるのだろうか。これらの解は、まるで、決まり文句の不動産の販売チラシのようで、いかにも表層的に聞こえる。経済的なコストと庭の効果のグラフを作ることになるのだろうか。金額を横軸としても、庭の縦軸とはなんだろうか。そして、なぜ、そもそも人々は庭を作り続けたのだろうか。庭は、当然、日本だけでなく、ヨーロッパにも、イスラムにも、ヒンズーにも、中国にもある。形は異なれども、庭という存在は、人類共通の「共有物」なのである。これだけ存在していて、その存在理由がわからないのでは仕方ない。ガーデンデザイナーなどという仕事柄にも都合も悪い。ガーデンをデザインすると言っておきながら、ガーデンがわからないのだ。
つまり、辞書的な、教科書的な知識はあるのだが、それらは庭を学術的に捉えているだけで、作り手として、心の底から信用する気にはなれない。また、同様に、庭の様式論、 或いは市場価値のような情報も氾濫するが、これらも庭の表層を漂うばかりで、私の問い、つまり「庭とは何か」の答えにはならないように思える。この問題は、庭作りに携わる仲間だけではなく、庭に関心のある方々(庭の好きな方、庭の嫌いな方)にも知っていただき、出来れば共に考えていただきたいと思い、本小文を執筆、公開することにした。
本小文では、「庭」或いは「庭の存在意義」の問題が、何故現代に於いて切実な問題になるのかをまず、冒頭に述べる。次いで、庭の発生と変遷をたどりながら、東洋に通底する庭の普遍的本質を求めたい。更に、実際の庭作りの現場から浮かび上がる意味や思考を具体的にあげ、その源泉を探る。最後に論考の総括として、当初の目論見である、現代に於ける庭、そしてその存在意義を示したいと思うが、現時点では、それは庭の周縁にしか過ぎないのかもしれない。だが、とりあえず出発したい。
庭師を苦しめるグリーンなるもの
平成になる頃、若いお客様からこんな言葉をよく聞くようになった。「庭は要らないけどグリーンは欲しい」。その背中を押すように、親御さんらしき女性が言う。「庭なんか作ったらお金が掛かるばかりだから作らない方がいい」。内心、「ごもっとも」と思う。余談だが、庭木の手入れはそれなりにお金が掛かる。大きな松の木なら一人前の職人が二日費やすなんていうのは普通で、それを最低でも毎年一回行わねば、松の樹形が乱れる。一回に松の剪定だけで四万円掛かるとすれば、その後五十年手入れして約二百万円費やすことになる。嘆かれる気持ちも分からぬでもない。ただ、松の弁解をするならば、松は剪定し手入れを続ければ、五十年経ても、大して太りもせず同じ姿で楽しむことができる。長く楽しめる木なのだ。しかも、一年を通じて、同じ姿。桜が一般的に三十年から五十年で大木になり、朽ちることを思えば実に耐久性のある木なのだ。桜は、さらに剪定しても大して美しくならない。
しかし問題は、若いお客様の言葉だ。私たちには、十分「庭=グリーン」なのだが、お客様にとってどうも、グリーンと庭は別物になっていることに気付く。果たして観葉植物のことなのか。はたまた多肉植物のことなのか、判然としない。しかも、その声は日増しに大きくなって来た。住宅の狭隘化も手伝って、これからの庭は狭くなる。庭師も、観葉植物やインドアグリーンと言われる世界を取り入れて行く必要があると場当たり的に考えて、実際その頃、随分観葉植物の研究をしたりしていた。だが、ある日、簡単な事実に気付き、あっと声を上げそうになった。新築の外構と庭を考えていた時のことだ。新築の外構や庭を考える場合、当たり前だが敷地図面と家の部屋割りなどを描いた図面を基本にして描くのだが、「座敷」がないことに気付く。何を当たり前のことをと庭関係以外の一般方々は冷ややかに思われると思う。今時、和室はあっても座敷のない家の方が当たり前なのだ。和室のある家さえ珍しい。珍しいついでに畳も琉球畳などになっている。
しかし、庭関係の方ならご存知のように、実は庭は「自立的存在」ではなく、座敷と対になって存在するものなのだ。(この辺りは、後ほど詳細するのでそれより私の驚きに共感して欲しい)庭と座敷は切っても切れぬ主従の関係と言い換えてもいい。座敷を主人とすれば庭は家来なのである。その主人たる座敷が、平成時代には「消失」したのだ。失踪し帰らぬ人となったのだ。主人が消えた家来たる庭は、もはや庭でなく、ただのグリーンになったのである。庭として主従の関係を結んだのに、主人が失踪し、行き場を失った庭は、庭としての資格を失い、グリーンとなってしまったのである。
あの不可解なグリーンという言葉は私たちに大きな断絶を指し示してくれていたのだ。
庭に立ちはだかる平成
平成という時代を後の歴史学者はどのように定義するのかは判らないが、五十年後、百年後には大きな転換点と記されると思っている。個人的には数百年に一度の大きな地殻変動だと思う。平成という時代は、概括すれば、江戸後期から昭和まで続いた一つの時代の終わりを示している。人口の減少、右肩上がりのインフレ経済は終焉、家制度の壊滅、超核家族化の進行、GDPの伸び悩みによる生涯所得の減少および停滞、終身雇用の崩壊、未婚率の上昇、その断層はいくつも列挙できる。まるで、地表に表れた断層の露頭を垣間見ている様相である。例えば、卑近な例を挙げれば、最近流行っている墓じまいという言葉が象徴的だと言える。武家から一般大衆にまで広がった江戸期からの家制度は崩壊し、平成は、墓を放棄する社会になった。昭和の時代まで多くの人には考えられなかった現象だと言える。それまでの暮らしは、「家」を守り、まるで墓守をすることが史上命題でもあった。生きることは墓守をすることと言っても過言ではない。そういう社会とは別種の社会が現れた。継続困難社会とも、断絶社会とも言える。つまり、今まで無意識に継続し、信頼してきた社会の形が大きく秩序変更されたとも言える。家族や親族でお彼岸やお盆に墓参りなどというのは、思い出のシーンになろうとしている。そして、庭にも平成が立ちはだかってきた。リビング中心の家は、庭の必然性を疑問視し、男女雇用均等社会でのダブルインカム世帯は、庭の手入れを拒否し始めた。庭は、もともと厄介なものなのである。気付かぬうちに、植物は繁茂し、草は茂り、おまけに、害虫と呼ばれる毛虫が湧き出す。ペットを飼うと、毎日、散歩させたり餌を与えたり、トイレの世話をするように、実は庭は手のかかる存在で、同じく庭を「飼う」気持ちがないとやっていけるものではない。
また、一方庭は元来、世間体とか見栄とか家構えのアクセサリー、演出道具という役割の片棒を担いできた。その家は、平成になり、「家制度の家」ではなく、個人の寝食小屋になったのだから、世間に見栄を張る必要も無くなった。犬や猫を好きでない人が、ペットを飼わないように、庭も要らない、と思う人が出てくるのは当然の帰結なのだ。こうなると「私は庭職人です」などと言っても、後二十年もすれば「伝統技芸の人」と思われるか、ただの作業員の呼称となるのではないかという気がしてくる。
庭はこのまま生き絶える絶滅危惧種に指定されていくのだろうか。そして、愛玩動物のように細々と生命をつなぐのだろうか。そこは、当然庭業界の一員として反論したくなるのだが、困ったことに庭の姿は、霞んでいるのだ。
庭はどこから来たのか(日本編)
庭は、一般的に日本では鑑賞する場所と考えられがちで、有名な竜安寺の石庭でサッカーをしようとは大抵の方は思わない。実際、据えられた十三個の石は邪魔で、深い白川砂利は走りにくい。塀も球技にはやや低い。余談はともかく、鑑賞して心を落ち着かす、鑑賞を通じて思索にふける、自然の機微、もののあわれを見出すという、なぜか、やや高尚な場所に祭り上げられている。しかしながら、私たちの現実の庭は、もう少し切実である。庭と呼ばれる敷地を使って暮らしに必要なコトをしなければならならない。物置や布団や洗濯物干し、靴洗い、小さな子供がいれば夏にプールを置く場所として使いたい。それは、古代の人も同じだったろうと思う。そんな疑問に対して、庭園研究家の今江秀史氏はその著書※1の中で、平安時代以降の庭を「大庭」「屋戸」「坪」「島」に大別し、小学校に例えて、庭の説明をされており大変わかりやすい。現在では、どの言葉もあまり、聞き慣れない言葉だが、この言葉全体で平安時代の庭全体を指す。まず、小学校の運動場にあたるのが「大庭」。イベントなどを開く場所。校舎に囲まれた場所を「坪」。今でも、坪庭という言葉は残っている。また、自転車置場や物置がある余った敷地を「屋戸」。そして校庭に作られた池や築山(人工的に作られた土を盛った場所)を「島」と区分されている。
つまり、敷地内の建物以外で余った余地全体を庭と捉えた時、島以外の余地は、殆ど何らかの目的のために「使われる場所」であったとされている。見る場所ではなく、使う場所だったのだ。
私たちが、現在、庭と読んでいる場所は、庭の一部に過ぎなかったのだ。実は私たち同様、家の周りの敷地で、生活に必要なことを行っていて、それも庭だったのだ。私たちが今「庭園」と呼ぶ庭は、過去には「島」と呼ばれ、江戸時代には「林泉」と呼称される庭の一部でしかなかった。
そして、その後、大庭や坪は消えていく。理由は簡単で屋外で行っていた行事を屋内で行うようになったからだ。坪と呼ばれる場所は、舞台が置かれ舞踊を披露していた。囲まれているので鑑賞しやすかったからだ。また、大庭には、運動会などのイベント時に今でも行われるテントのようなものが張られて催しがされていた。しかし、時代の変遷により、これらは、屋内化が進み、消えていく。ただ、今でも京都御所や東大寺の大庭を見るとその面影が残っているのが読み取れる。また、時代劇で出てくる奉行所などの「お白洲」もこれらの名残だと言えるし、先ほどの竜安寺の庭も、お白洲の後に作った枯山水だと考えることもできる。
このように考えると現代の庭は、駐車場やアプローチなどにしている屋戸と島が生き残った場所と言える。また、庭は、建築の様式や工法の変化で姿を変えるものであることも指し示している。つまり、庭は庭として独自に「自立」した存在ではないのだ。
※1 今江秀史著 「京発・庭の歴史」 世界思想社 2頁
島の発展と屋戸の切り離し
室町、鎌倉という時代に降ると、いわゆる寝殿作りの貴族の家から、武家を中心とした書院作りの家に変化していくこととなるのだが、その中で島(庭)が何故これほど発展し、普及したのか。という疑問が出てくる。そこに、平成で失踪した座敷が関わる。この書院作りの家でこそ、座敷が誕生するからだ。武家を中心とした書院作りと貴族を中心とした寝殿作りの大まかな違いを列記すると次のようになる。
1)柱が円柱から角柱に(ピタッと閉まる)
2)天井が出来た(断熱性、保温性が高まる)
3)畳が登場(居心地がいいベット)
4)障子、襖が登場(御簾に比べ、間仕切り完璧 プライバシー確保)
5)書院と呼ばれる床の間が出来た(陳列棚の誕生)
寝殿作りではあった対屋も消え、渡り廊下もなくなっていき、よく見ると、昭和時代の一般の田舎家の原型ともいえる家となってくる。まるで体育館のように伽藍堂であった寝殿に比べれば間仕切りも出来、実際的で住みやすい家に変化したといえる。周囲に防衛のための塀や土塁を築いていたが、家としては個人の邸宅となったと言える。この時、坪が消え、大庭もなくなり、屋戸と島が残る形になってくる。
書院造りの中で、特に重視された場所が、畳を敷いた(板間の場合もあるが)座敷=書院(主人の間)であり、それと一対を成す「島」(庭)だと言える。
室町後期からの下克上の中で成りあがってきた武士の家である書院造りの家屋は、現代のような家族の寝食専用住居ではなく、オフィス兼住居であったことが窺い知れる。南側の日当たりの良い部屋に主人の書院(書斎)が置かれると共に、調度である床の間を配置し広い座敷、中の間が大抵あり、人々は北側の暗い部屋で生活している。家族中心主義の現代の住宅では考えられない仕様となっている。
座敷は、書院の床の間、庭と一対となり、客を迎え入れる特別な空間として家の中心施設として鎮座することになる。実際、現在でも、庭は座敷に座った客人の目の高さで作られることを基本としていることにその名残がある。
下克上社会というのは、実力主義社会であり、一種のデモクラシー であるとさえ云えるが、実力至上主義社会の武家にあっても、武力だけで社会的支配を確立することは、難しい。武家であっても文化や教養を持つことは、旧勢力である貴族との関係性上重要であったろうし、武家にとっても他者と差別化するための文化戦略として機能していたと考えられる。そこに、床の間での「モノ自慢」と「庭自慢」が加わったのではないだろうか。下克上の魁であった越前の朝倉氏が京文化を積極的に取り入れたことがひとつの証左だと思う。
合理的(チカラの論理)には、必要なかった庭(ここでは敢えて、京風庭園と呼ぶ)も、彼らにとっては、床の間の調度と共に、自身の文化的見識の誇示として作用したと考えられ、その欲望を背景として、島の発達を促したのではないだろうか。このことは、戦いのない時代の武家屋敷で大名庭園がますます発達することにも関係していると思う。
確かに、当時、流行した禅思想は、武士の生き方にマッチしていたし、千利休を代表する堺商人との結びつきは、軍事的・経済的な意味をあっただろうが、背景には「文化的優位性」の獲得もあったのではないか。と考える。
島(庭)は、そのため、家格、教養、見識、経済力、つまり権力や権威を暗に示す道具として発達したのではなかろうか。こうした風潮は、太平洋戦争後、民間の間でも続き、昭和時代になってからも経済的に富裕な家庭が、広大な日本庭園や茶室を持たれていた経緯はここに端を発しているのではないかという気がしてならない。
また、島の発達は、屋戸と島の分離をも促したと思える。島と屋戸は同じ庭として出発しながら、全く別種の役割を果たしている。屋戸は、実際的な生活に密着した、言わば普段着の場所であるのに対して、庭は客人を迎える晴れ着の場所として発達する。同じ庭でありながら、その各々の場所での思惑が全く違う。島は、様々な形式はあれども、池を掘り、築山を作り、石を据え、樹木を配し、和歌で歌われた景色を再現したりして、大自然を小さな箱庭として縮景する。つまり、「見立て」という抽象化が起こり、「小さな自然」として庭園風景を作る。砂利を海と見立てたり、池に水を引く遣水を山奥の清流と見立てたり、浮島を蓬莱山や釈迦に見立てたり、見立てによる抽象化が起こるのに対し、使う庭である屋戸では、その必要がないことになる。このことは、現代風に言えば、外構、エクステリアと庭の分離に相当する。使用する庭、使用しない庭で別れていくのは当然で、現代では、よりそれが明確となっている。現在の分類では、駐車場、カーポート、アプローチ、塀、自転車置き場、門柱は外構・エクステリアと呼ばれ、庭と呼ばれる部分は意外と少ないのだ。余談だが、庭師や庭職人といえば、ややクリエイティブ・アート系、エクステリア職人といえば、やや作業系に見えるのは、この庭の性質の違いによる世間の誤解であることを付け加えておく。クリエイティブというものは本来業種でできるものではない。そう見えるだけ。私自身、ガーデンデザインなどというと、たまにややこしい目で見られので、植木屋と自称してこの難を避けていることを付記しておきたい。
また後、面白いことに、実は生垣も「外構」に分類されている。これは、実際に作業する植木職人にも奇妙な分類に感じるのだが、「使う」という点では納得できる。
そして庭は途方に暮れる
明治時代に導入された「洋風」による、応接間設置後も、座敷は私たちの一般家屋の中にも生き続けてきたが、平成は、容赦無く座敷を追い出し、リビングを迎え入れた。庭は昔懐かしい大沢誉志幸の歌の如く、途方に暮れることになる。島として発達してきた庭の存在理由は不明になり、庭はアイデンティクライスシスを迎える。私たちも実は、この先どうすればいいの、ということになる。座敷のない庭は、庭「のようなもの」、庭「らしきもの」、庭「っぽいもの」となっていく。果たして庭は今後、このような疑似的な存在でいいのであろうか。座敷の喪失で、庭は消えてしまう。そんな浅い存在だったのか、という疑問が湧いてくるのである。しかし、庭は世界の共有財産である。狭い日本の文化を超えて、世界を見てみよう。そういえば、世界の庭は、座敷などなくても存在しているではないか。
庭とガーデン(海外編)
庭という言葉と非常によく似た言葉として「garden」という英語がある。庭という日本語は、島、泉林、山水と昔呼ばれていた。しかし、一説には、私たちが使う「庭」という漢字は、英語の「garden」いう言葉の対訳語として明治時代に引っ張りだされたという説もあるくらいだ。庭という言葉は、「廷」(建物)周囲の広い場所という意味があり、この広い場所で祭儀が行われていたという。中国の記録にそういう意味で「庭」という言葉が登場する。
古くは、「ニワ」は「ニハ」と呼ばれていた。庭という漢字には、「にわ テイ」という音訓読みがあるが、もうひとつ「バ」という音が当てられている。このバという音は、今私たちが使う「場」と繋がっていて、広場、市場という言葉を聞けばイメージが湧くように、「バ」は、広く平坦な場所を表す言葉と繋がっている。
一方、ガーデン「ga―den」もまた、囲まれた土地くらいの意味しか元は有していないという奇妙な一致があるようだ。但し、想像だが、庭とガーデンは広さが異なっているように思える。ガーデンが縄張りや支配する場所という比較的大きな面積を持っていると思えるのに対し、「廷」の字を有する庭は、貴人の家の周囲を表す程度に思える
この庭とガーデンの広さの違いを実感する逸話が残っている。明治十一年に日本を旅行したイギリスの旅行家 イザベラ・バードは、その旅行記※2で、訪れた米沢地方の田園風景の美しさ、豊かさを賞賛しているのだが、その表現は「アジアのアルカデャ(桃源郷)」であり、「エデンの園」のようだと褒め称えている。
エデンの園は、「園」と言われる確かに広い場所だが、英語では、「orchard」ではなく「The Garden of Eden」であり、彼らにとっては、庭に相当する。この広さの感覚は、私たち日本人にとっては難しい。私たちにも里山の美しさを理解することはできるのだが、それは決して「庭」ではない。しかしながら、イギリス人であるバード女史には「楽園=庭」という世界観には適合しているのだ。「彼らの思う庭=園」の大きさのイメージが異なると同時に、庭に求める質的内容が私たちと随分異なっていることが読み取れる。
また、この質的内容について付記すると、聖書によく出てくる植物と万葉集に出てくる植物の比較をみると実に面白い。
聖書での主な植物の頻度順
①ブドウ(百九十三回) ②コムギ(六十回) ③イチジク(五十二回) ④アマ(四十七回) ⑤オリーヴ(四十回)⑥ナツメヤシ(二十七回) ⑦ザクロ(二十六回) ⑧オオムギ(二十六回)
日本の万葉集での主な植物の頻度順
①ハギ(百三十八回) ②ウメ(百十八回) ③マツ(八十一回) ④モ(藻)(七十四回) ⑤タチバナ(六十六回)⑥スゲ(四十四回) ⑦ススキ(四十三回) ⑧サクラ(四十二回) ※3
ヨーロッパ世界では、一神教に端を発する「人間(人工=art):未開(自然=nature)」という二項対立的世界観を持ちながらも、日本のように菜園や果樹を庭文化から排除していない。聖書に出てくる植物は、日本人から見れば、実に生活に密着した有用植物であることに驚かされる。彼らにとっては、なぜか高尚な日本の庭と違い、暮らしやすく、果実が豊かで、安全で快適な場所(領地)を庭と感じているように思う。
そうなると彼らのガーデンの始まりを考える必要が出てくる。一体ガーデンはどこからきたのだろうか。
※2 イザベラ・バード 時岡敬子訳 「イザベラ・バードの日本紀行」 社学術文庫 320頁
※3 中尾佐助著 「聖書と万葉の植物 週刊朝日百科 世界の植物」 朝日新聞社 3323頁
gardenの登場
現在のガーデンに続くものは、世界的には約八千年前。移動生活から定住生活に移り、農業が始められてから出来たのではないかと云われている。昔のことなのではっきりとはしていない部分も多いが、メソポタミアに始まり、エジプト、ペルシャへと続き、相互に影響してガーデンは発達している。
確かに、考えてみれば、農業の絶対条件は、水の確保であり、水を操れる技術(灌漑)、平坦な土地、さらに害獣から作物の防護が必要になる。ここに「garden」の原義に近い空間が生まれてくる。また、農業を行うことによって、狩猟採取生活ににあった原始共産的な世界が終わりを告げる。農業による大きな人口を養う力は、富の蓄積と偏在を生みだし、所謂、「文明」が世界史に登場してくる。族長や酋長は「王」として飛び出してくることになる。この文明の登場と共に、ガーデンが作られていく。それは何故なのだろうか、推論してみる。
農業の発達は、例えば、栽培品種の多様化、交易による外来植物の増加、園芸技術の進展などが挙げられるが、これらは全て庭を作る背景条件として適合するように思う。平な土地を作り、柵で囲み、好きな植物や果樹を繁茂させ、さらに珍しい植物なども植え、水を遣り育てる。安全で快適で好ましいその場所は必然的にガーデンに到達するように思えるのだ。
また、もう一つの重要な点に着目したい。これらの諸要素は、人間が世界を作り変える技術・知識を会得したと言えることだ。それまでの採取生活では、自然の恵みを「受動的」に受け取り、それを与えてくれる神々や精霊に感謝することを基本にしていたと思われるが、人間が「能動的」に自然を作りかえる農業(ある種の自然破壊)では、人間が自分たちが思うように主体的に自然を作りかえ、自分たちの欲する世界を目指すことになる。庭作りという行為にも、まさにこの点を深く抱えている。自分たちにとってどのようなスタイルであれ、好ましい場所に世界を作り替える行為に他ならないからだ。そのように考えれば、「人間が考える自然=不自然(art)」の中から庭が出現するのは必然であったろうと思う。
このことは現代の庭とも通底している気がする。現代人は庭に何を望むだろうか。それは、ひとつには安全であること。食物や植物が豊かであること。美しく好ましいものに囲まれていること。また、ここに宗教的要素を付け加えるとすれば、神(精霊)と結ばれることとなるだろう。農業による技術獲得と、その技術がもたらす自然への能動的世界観。この二つが文明とともに庭を登場させた理由と思えるのだ。
その姿は、やがて、メソポタミアのギルガメッシュ叙事詩の中に表れ、同じく、バビロニア空中庭園、ギリシャのアルカディア、紀元前六世紀のインドの祇園精舎、そしてエデンの園へと姿を変え、受け継がれていく。ただの「囲まれた平らな場所」が、理想郷、桃源郷、楽園、オアシスと変貌していったのではないだろうか。庭は、自然の中に求める人間の幻想のカタチとも言える。人が夢みる場所なのだ。
エデンの園へ
ヨーロッパで一番有名な理想の庭は、おそらく「エデンの園」だろう。しかし、実際のエデンの園は記述が少ない。幸福の木(樹種不明)や知恵の木(多分リンゴの木)がわかっているくらいで、その形も大きさも、わかっていない。実に空白の多い庭なのだ。そのため、人々は、その余白を自分らしく埋めることができる。現実のエデンの園は、記録にないのだから、自分で夢みることが許される場所でもあるのだ。ヨーロッパの庭では、よくギリシャ風の塑像や噴水が散見されるが、不思議に思われた方も多いと思う。キリスト教世界で、なぜかギリシャの神々が祀られているのだ。日本にある洋風庭園にも同じように塑像が飾られているのを目にする。
結論から言えば、これは、目に見えぬエデンの園を追い求め、ギリシャのアルカディア(理想郷)と結びついた結果だと考えられている。そのためギリシャ風が輸入され、ギリシャの多神教的神々もエデンの園に引っ越して来たという訳だ。日本の庭にも弁財天や不動明王というインドの古層の神々や仏様、蓬萊山だのが引っ越してきているのと同じだと言える。
創世記に記されているエデンの園は、最初の七日間が終わった後、アダムが泥から創られ、その後アダムの管理下で植物が植えられていくことが記されているが、実は創世記では最初の二日目に植物が創られているので、エデンの園にある樹木は、聖書に出てくるような人間にとって有用な植物であろうことが想像される。
このことは、エデンの園が自然の森ではなく、まさに人間の代表であるアダムが作った庭であることを示している。最初の人類は、庭師であったとも言える。イザベラ・バートが言うように、豊かな果実や花に囲まれ、美しく安全な場所。人間が夢見た「自然=ガーデン」なのである。そして、その姿は、実は家や建物に依存した存在ではなく、理想の自然として「自立した」存在であることがうかがえる。
投稿日:2021/08/19