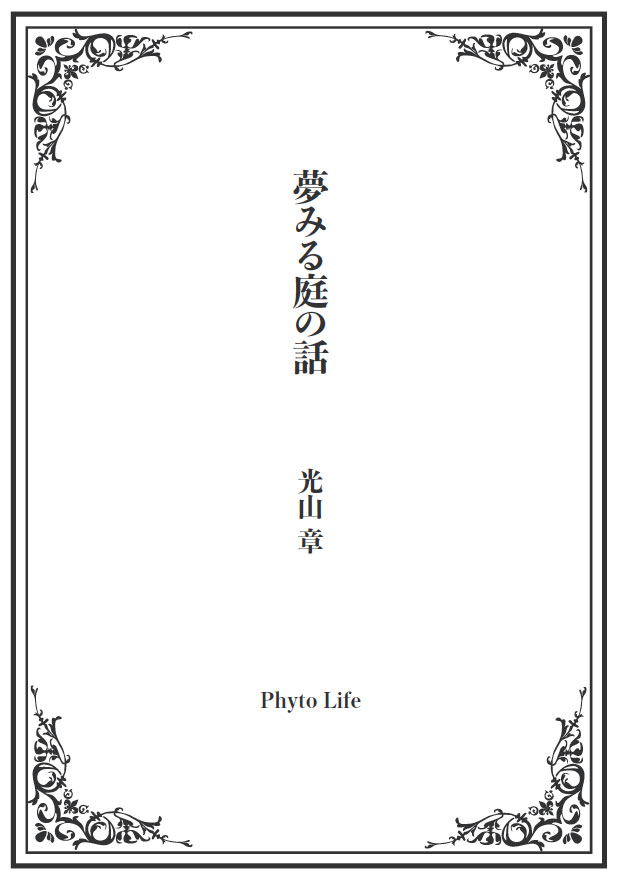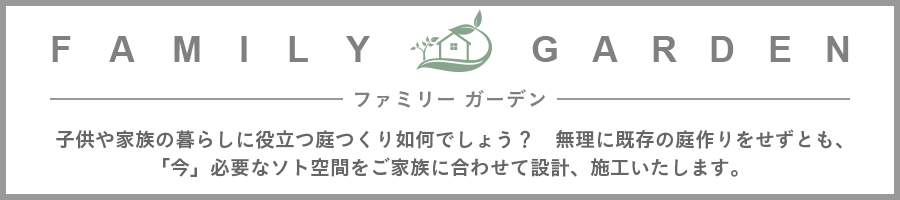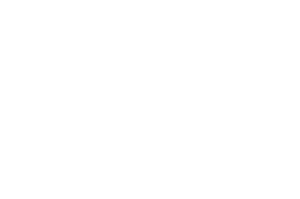夢みる庭の話(後編)
この度、これまで考え続けてきた「庭」或いは「庭の存在意義」の考察をまとめた冊子を発刊いたしました。あくまで現段階でのまとめではありますが、私たちの集大成になったと考えております。ホームページとPDFも併せて公開させていただきますので、お読みいただければ幸いにございます。尚、ホームページでは前編と後編で分けて掲載しております。
隠された庭の本質へ
庭およびガーデンを見てきたが、その庭にはまだ見えぬ、隠されてきたものがあると感じている。庭は、有用植物を集めた博物館ではない。安全な敷地だけでもない。そして、合理的に作られるだけのものではないのだ。よく考えれば、庭はいつも、美を求められる。
その美は、国や地域、個人でも異なるが、美を求めない庭はない。どの地域でも美を感じない庭はその存在価値さえも疑われるのだ。美とは何かと言うことが問題ではなく、美を求める心の場所として庭が選ばれていることが問題である。家や他のものにも美を人は求めるが、庭は、美のみを目的にしていると言えるほどの絶対条件となっている。
さらに庭には、前述したようなギリシャの神々だけではなく、東洋の神も、また、キリスト教以前の古い神々、ゴブリンやカーゴイル、小人などの精霊たちが集まる場でもある。それはなぜなのだろう。一神教の強い神ではなく、多神教の弱く小さく、自由な神々、それは精霊とかスピリッツと呼ぶ方が似合っている。その精霊が庭に集まってきている。
そして、美や精霊を呼び寄せる庭は、普段私たちが意識していない古い思考で作られていると言うことも重要な事実だ。庭を作る思考は、実は自動車やビルを作る思考と全く違う思考形態で作られている。その思考は、恐らく、無文字社会の思考であり、未開民族に残る思考なのだ。では、現代の家作りと庭作りの対比から、その思考を探ってみよう。
現代の家作りの思考
庭作りと家作りは、元来、同じ「手作業」だった。しかし、現在ではその姿を大きく異にしている。戦後、住宅問題の解消、高度成長期のマイホームブームを背景に、戦後、家の建築は、近代化の道を辿り、工業化されてきた。
従来、家の建築は「棟梁」と呼ばれる職人を中心に地元の人間である「男衆(おとこし)」などを使いながら、行われていたが、建築基準法の施行、建築士を中心とした徹底的な分業などを背景に、パネル化、プレカット化、乾式化などが進み、予定通りに合理的に産出される「製品」として取り扱われるようになってきた。まさに「工業化」されたと言える。
建築現場から棟梁がいなくなり、作業員という人々が家を組み立てる、まさに工場労働と生産の関係が成り立つ。実際、ある住宅の新築現場で私自身が体験したことだが、お客様が家の「棟上げ」を行われるというので、参加させて頂いたことがある。神主の方が来られて、棟上げが始まるのだが、肝心の「棟梁」がいない。現場におられた大工さんに「棟梁役」をお願いすることになるのだが、彼は日雇でその日来られていた大工さんであったため、非常に恐縮されて式がなかなか始まらない。そこを家主と神主の御説得で無理やり棟梁役を引き受けて頂いた記憶がある。現在の家建築を象徴している出来事だと言える。
予定されている材料を工期に従い現場へ運び入れ、分業体制の中でそれらを組み上げるという製作手法となるため、一方では、徹底的なクラッシュ&ビルドを行う。古い家の材料を使うことはなく、すべて撤去されるのだ。
戦前の日本の地方都市では、棟梁を中心とした一部の専門家と村人で古い家屋を取り除き、その古材を再利用する「手仕事」を通じて、家を再生させていた。しかし、個人の技術に左右される大工仕事、天候に左右されやすい左官仕事など、非効率的建築手法は現在、ほぼ姿を消そうとしている。通常、一軒のそれなりの屋敷を建設するためには、一年は優に費やしていた。特に土壁は、下塗り、中塗り、上塗りを乾燥させるためには一年は優にかかる湿式工法で、工期が長く、安定しない。そのため、所謂「左官」の領域も随分と減った。そういう意味では、現在の家は、塗る場所のない「貼る」だけの家であるとも言える。そして、古代から手仕事の産物であった家はなくなり、工場で産出される「箱」になったと言える。
庭作りの思考
一方、庭作りはどうだろうか。庭作りは、戦後の工業化、近代化の波に取り残されたカタチで現在も続いている。使う庭としてのエクステリア・外構の思考がメソッドとして入ってきて随分図面化されてきたが、本来的な庭作りでは、ほぼ図面化されないメソッドで庭は作られてきた。その原因を辿れば、幾つかの要因が考えられる。ひとつには、植物などの生鮮品を扱う難しさ。生物を工場ラインに乗せることは非常に厄介なのである。もうひとつは、庭を規格化することが困難であることだ。敷地のカタチや方角に左右される庭は、「坪」及び「平米」の単位で価格を標示することができる家建築に比べ、庭工事ではそれが表示できないのだ。次に考えられることは、石や土、樹木など「自然物」を取り扱うこと。自然物は、大小様々で、図面化したところでそれと同等のものを揃えることは難しい。品質も揃っておらず、材料が均一化できないため、工業化には適していないと言える。
そして、最後に「美」を取り扱うこと。庭の美は、その場で追い求めながら作られていくものであり、完成予定図に向かっていくものではないのだ。この感覚は「手繰る」という言葉で表現するのが最も近い。手で美を探しながら、見つけていくのだ。実際、自然物を扱うため精緻な完成模型を描くほど制作は困難となってしまうジレンマを持っている。
このことは、制作体制にも当てはまる。家の建築の場合、ご存じのように、まず、最初に行われるのは、解体、次に、整地という土木、家の基礎、プレカット材料の組み上げと進む。そこに参加する人々は、別事業体に所属するそれぞれの職人で、一貫しているのは、建築会社と設計士だけとなる。
一方、庭仕事では、設計者である庭師も古い庭の解体、樹木の移植などプレイヤーとして常に関わる。庭仕事では、多くの場合、古い庭に残る材料はリユースするため、(廃棄する場合もある)、再生させる庭のリソースの確認として解体は、重要な意味を持つのだ。現在では、庭にも設計図面を求められるようになったが、過去には、図面というよりも大まか構想図が示されるかどうかという具合だった。少し長く難解だが、庭師の仕事の進め方をご理解いただくために、竜安寺の石庭を考察した、フランスの美学者であるダニエル・シャルルの文章の中の庭師の仕事ぶりを書いている記述を紹介したい。
「石庭について、造園上必要な前提条件としての設計図を画定したがる傾向が斥けられる。このことは、例えばラングドン・ワーナーという筆者が指摘した身体性という所見を裏書きする。それによれば、日本の庭園設計者は、「幾日もの間、一日の様々な時刻に、様々な天気のもとで用地に眺め入りはしても、……殆んど平面図やデッサン」を用いることがないというのである。彼は、トレースするというよりは、地図を作製するというべきであり、「歩きながら、地面に立てて行くための小型の杙を入れた籠を持っている」。つまるところ、 彼の仕事は地面を響かせる―ここ、かしこから生ずる生の音に学ぶーことなのであり、知的もしくは抽象的なプログラム化の全てを身振りよってショートさせてしまう、巡回的な、音楽的な、身体的な作業なのである。さらに言えばその行程は歩行に外ならず、線引き、測量というよりは周回運動であり、大地を統御するよりもその起伏に従順に、遍歴することなのである。庭師の残す標は、プランニングあるいは測量図を必要とはしない。それは、記憶を助けるだけの標である―そして、それは忘却が支配していることのしるしである。」 ※4
おそらく庭作りの仕方を見たことがない施主の方であれば、何か祈りの儀式か、祭礼でも行っているかのように思われると思う。机の前に座り、CADで設計図を描く設計士とは随分かけ離れた仕事のやりようなのである。このようなやりようでは、確かに近代化できない。
庭ではこのように前近代的ともいえる「手仕事」の思考が今でも残っている。例えば、庭石を例にとれば、庭石はある時は、景石となり風景を縁取り、土に埋めれば飛び石、土留めに使えば石垣と変化する。同じ素材を「据える」「埋める」「積む」「置く」「立てる」という手仕事で意味や役割を変化させるのだ。このことは、平安期書かれた「作庭記」にも表現されており、作庭記は、「石立」から始まるのだが、現代までの間、庭作りの思考は実は全く進歩していないと言える。このような思考作法は、現代建築には残っていない。
※4 ダニエル・シャルル著 渡公三訳 「 安寺石庭のための註 」 現代詩手帖 ジョン・ケージ 4月時増刊 思潮社 141頁
庭作りに残る古代の思考
庭作りには、先述したように、現代でも、庭石や樹木を再利用する思考が残っている。これを現代的なリサイクルと呼びたいところだが、そうではない。庭作りに残る「手仕事」の跡は、縄文時代の縦穴式住居にも、未開社会の家作りにもある考えに通底する古い思考だからだ。
目的は、庭を作ることだが、その庭は設計室で合理的に図面化されたものでなく、その場で材料を見繕って、再構成するというものだと言える。庭には明確な完成図はなく、石や木を触りながら、浮かび上がるイメージを辿りながら臨機応変に変化して行く。そのため、現代的な「完成」はなく、本来、その場にあるものであるがままに作られて行く傾向があり、気に入らなければまた、同じ行為で作り直していくのだ。幼児が積み木遊びする様に実に似ている。古代の人々が、自然の中からいくつかのモノを取り出し、それを組み合わせ、モノを作る思考に実に似ている。
キリスト教など一神教社会では消えてしまったが、これら手仕事の世界は、モノを物質としてだけでなく「擬人化」する思考も含む。それは、庭の景石を据えていく思考にその痕跡が残っている。
例えば、石を据える時、庭師は「石の顔」を探す。その石の最も見栄えの良くその石らしい部分を「顔」と擬人化し据え、次に据える石は、最初の石に任せる。最初の石に「意思」を見出し、石との対話にも似たコミュニケーションの中で庭作りを行っていく。ただの鉱物であり、無生物をまるで生き物のように扱う。庭作りとはこのように世界を作る手法であり、思考なのだ。積み木を触っている内に、知らず知らずに、それが何かのカタチに見えて、様々な積み木を連鎖させ、積み上げ、また、崩しながら、自分が作りたい世界に到達する。そのような感じなのだ。この作業は、音楽家に近い思考だとも言える。最初の音をドの音として次の音をミ、そしてソと置くことによって、個々には意味のない音が、旋律や和音として機能し「姿」を表してくる。人間は、自然界に存在する様々な音から、任意の音を抽出し、それを組み合わせて「意味」を見出す「思考方法」を元来持っているのだ。この思考は、庭以外にも音楽や言語、神話や伝承に残る思考だと言える。
言語は、無数にある音から日本語であれば、五十音ほどを取り出し、これを組み合わせ「言葉」を作り、また、神話では自然界にある様々な事象から、鳥やクマ、ヘビやワニなどを取り出し、これらをつなぎ合わせ「物語」を作る。民俗学者であり構造主義者であるクロード・レヴィ=ストロースはこれらを「野生の思考」※5と名付け、手仕事を「ブリコラージュ」と呼んでいる。庭作りの思考は、現代人である我々が普段あまり使わず、忘れてしまったかのような古代の思考の上に成り立っているとも言えるのだ。
一見すると、もの作りでは、同じに見える家と庭だが、そこで使われている思考は大いに違っているのだ。家作りの思考を新しい思考、庭作りの思考を古い思考と名づけることもできるが、実は新旧ではなく、普段の生産的・合理的な仕事ではあまり使わなくなっただけで、現代でも我々が保有し併存した思考なのだ。それは手探りで、絵を書いたり、詩を書いたり、パッチワークをしたり、テーブルをコディネートしたり、服を選んだり、インターネットで調べものをしている時を考えれば誰しも行っているのだ。
※5 クロード・レヴィ ストロース 大橋保夫訳 「野生の嗜好」 みすず書房 22頁
依代としての庭
庭には、実に多くの精霊が集まってきている。先述したギリシャの神々、主神デウスや芸術の神アポロン、愛の神アプロディテなど多くの神々の塑像が庭には置かれている。そのほかにも、カーゴイルやニンフ、地下世界のドワーフやゴブリン、森の小人などもいる。日本の場合は、造園家であり庭園研究家の重森三玲は、日本のストーンヘンジとも言える神が降臨する磐座や磐境に日本庭園の始原を見出し、その面影のある石組みを称えている。余談ながら、日本の庭によく置かれている親子ガエルや信楽焼の狸は残念ながら昭和に入って流行した置物に過ぎない。
御神木や御神体として石や木の中に精霊を感じる思考は、日本では八百万の神として今でも広く知られている。しかし、先進国と言われる経済の発達した国では、こうした多神教的国家が少ないため、このことを「日本的」と解されているが、実はそうではない。一神教で覆われる前の世界では、世界中にも日本のように精霊に対する思考が残っていた。
世界各地には、世界樹神話というものが残っている。地域により、樹種も異なるが、大まかな世界樹に対する話は異ならない。
樹木というのは、冷静に考えれば、人間が地球上に登場するよりも古くから存在し、大きく、長生きであり、地下世界と地上、そして、天上界を繋ぐ偉大な生き物と言える。
「遠い昔、人間が地球上に姿を現わすはるか以前に、一本の巨大な樹木が天までそびえていた。宇宙の軸であるこの樹は三つの世界を貫いている。その根は地下の深淵まで伸び、枝は天の最上層に達する。地中から吸い上げられた水は樹液となり、太陽の光からは葉と花と果実が生じるのだ。その樹に沿って稲妻が走り落ち、雲を集める樹頂は豊饒をもたらす雨を降らせる。樹は垂直にそそり立ち、天上界と冥界の深淵をしっかりと結びつけている。樹の内部では宇宙全体が永遠に再生をくり返し、あらゆる生命の源であるその樹は、いく千もの生きとし生けるものを保護し養っている。根の間をあまたの蛇が這いずりまわり、鳥たちは枝で翼を休める。ほかならぬ神々さえもそこを住処としていた。」※6とされている。
世界樹は、このように見ていくと、命の根源であり、生命を養い、世界を繋ぐ依代として扱われている。世界樹自体が神ではなく、世界樹を通じて精霊が現れる依代なのだ。依代は、現代でも神が依つくものとして、樹木、石、柱など様々な形で神聖視されている。女性の姿に変えて、神の言葉を伝える巫女や能の舞台背景に描かれる老松もこの依代の一つである。そして、日本庭園の源流と言われる磐座もまた依代だ。植物は、生命として動物である人間の先輩であり、不死の力を秘め、巨大な体を持ちながらも、人々に果実を恵み、雨や酸素も与える存在であり。そして、天と地下世界を結ぶ存在だと言える。
日本のスピリッツで植物と石を代表する話は古事記に残っている。古事記にはコノハナサクヤビメ(木花之佐久毘売)という可憐な名前を持つ神がいる。名前の通り、草花の神であろうと云われている。彼女には、イワナガヒメ(石長比売)という姉がいる。名前の通り、石を表していると云われている。庭師から見れば、この姉妹は「庭」の神様にも見える。石と植物なのだ。一方、コノハナサクヤビメは、美しくも限りある命であり、イワナガヒメは醜くとも永遠の命を表している。現代人から見れば、石は鉱物であり、花は生物になるが、現代科学でも生物と無生物の垣根が実はないことが証明されてきたように、古代人が、石と草花を一つの命としてみていたことは極めて当然に思える。
一般の方々は、庭をご覧になるとき、美しい樹木や草花に目を奪われがちだが、庭師が最も腐心するのは石の扱いだと言える。石は、重く硬い存在だが、一方で「永遠」という力を持つ特異な存在であり、命あるものを逆説的に輝かせる役割をしている。石をうまく扱えないと、植物が活きないとも言える。庭つくりは、ただ、単純に石を置いたり、植物を植えたりする行為ではない。極言すれば、石と植物で「理想世界」を作る行為であり、こうした世界観のない庭は、庭と呼べず、植林・緑化に過ぎない。
庭作りを行う者にとって、このスピリットの話は非常に気になる要素を含んでいる。私たちは、例えば、数万種ある植物から適当に木や草花を選び出して植えているわけではない。当然、気候や土壌、日照でその場所生育できる植物は限られてくるが、庭作りは、生育できる植物を植えるだけの場ではない。庭作りは、先に記したように幼児が積み木を触っている内にそれを何物かに見立てて追い求め、辿るように作る古い思考によって本来作られるものなのだ。木を植え、石を組むが、石や木に目的があるものではなく、世界樹神話にみられるように、木や石を媒介者=依代として捉え、その背景の世界を探る行為ともいえるのだ。その背景とは、楽園や理想郷、自然風景の中の神々しい世界に「美を介して」触れる手段とも言えるのだ。花を介し、樹木を介し、石を介し、それらの織りなす世界の中に、様々なスピリットが舞い込む世界が庭であり、庭作りだと言える。
実際の庭作りの現場に携わった者であるなら、誰しも共通し、共有する体験をする。家の周囲に、石を配し、木を植え終わると、作庭前まで、地上に浮いていた家が、地面に強く結び合わされたように感じるのだ。この不思議な錯覚は、ほぼ作業した全ての人の胸に去来する。朝には工事現場であった場所が、夕方には、この地球の一角として佇むものと変質していく。綺麗に洗われ、水に濡れた石、風の通り道を示す樹木の枝や葉の揺らぎ、ひっそりと佇む草花の風情、ただ庭が完成したのではなく、庭が依代として何かを運んできていると感じる。
最後に、樹木と精霊の関係を非常に視覚的に捉えられる話を記す。1097年に生まれた藤原成通の日誌に残る逸話だ。彼は「鞠聖」とも呼ばれた蹴鞠の名人だが、彼の日記によると、蹴鞠の千日行を終えた夜、蹴鞠の精霊が彼の枕元に現れ夜物語をすることが記されている。精霊は、普段は柳の林で暮らすのだが、蹴鞠が始まると樹木から、フワフワと浮かぶ蹴鞠に乗り移るというのだ。すると、鞠は一層飛び跳ね、地上に落ちなくなる。今でも蹴鞠を行う場所には、四方に樹木が植っている。そして、成通卿は、蹴鞠場にある木は切った木では駄目で、必ず生きた木でないといけないと記している。この話では、スピリットが木を媒介(メディア)として私たちにの世界にやってくることが実に可視的に描かれている。精霊が蹴鞠に乗り移る姿が目に浮かぶようだ。
一方、庭作りの現場では、この作用が可逆的に起こっている気がする。つまり、木や石を通じて、精霊の世界につながるという感覚だ。この感覚が、先の家がその土地に結ばれる時に、私たちに蘇る古い記憶なのではないかと思う。もし私が、古代人だったら、庭が完成した時に、皆の前でこう叫ぶだろう「今、私たちが祀った木と石を通して、精霊が来られた。この家に精霊が宿られたぞ」と。
※6 ジャック・ブロス著 「世界樹木神話」 八坂書房 15頁
庭と美
人はなぜ美を求める心を持つのだろうか。客観的な美醜はともかく、人は誰しも美を求める心を持っている。白いプラスチックのプランターに植えられたパンジーにも、壮大な庭園にもそれぞれが求める美を追っていると言える。
最近では、芸術という摩訶不思議な衣装を着たアーティストなるものが溢れているが、才能や特別な能力、商品としての美などは関係ない。どれほどささやかでも、人はそれぞれ美を求める心を宿しているという事実が大切だ。この心は、なんのために付与されたのか、という問題だ。私たちは、農業を始めた八千年前から、労働と収穫を計算する数式的世界を持ち、合理主義を発達させ、さらに十七世紀以降デカルトから始まる個人の誕生によって、近代合理主義を主な思考として最も尊重している。そのため、長らく、大量の生産と大量の金銭が人間を幸せにすると信じられてきた。しかし、一方、経済的な豊かさや合理主義の追求だけでは、私たちは幸福になれないことを今や私たちは知っている。そんな時、美を求める心は、行き詰まった私たちの心に設置されてきたもう一つの窓のような存在ではないだろうかという気がするのだ。誰のためでもない美を求める心は、本能のように振る舞いながら私たちに必要な思考として働いている。評論家の小林秀雄は著書「美を求める心」 でこのように記している。
「私は、美の問題は、美とは何かという様な面倒な議論の問題ではなく、私たちめいめいの、小さな、はっきりとした美しさの経験が根本だ、と考えている。(中略)美しいと思うことは、物の美しい姿を感じる事です。美を求める心とは、物の美しい姿を求める心です。」※7
私たちは、論理性や合理性を働かせながら、一方、美を求める心も働かせながら生きている生き物だと思う。その心の奥底には、論理性や合理性のない、全く別種の思考が眠っている。純粋にそのものが美しくあれと願う気持ちと言っていいかもしれない。庭の中には、その気持ちが眠っている。定型化され、商品化された美ではない。一人一人の心の中に発する、この世界が美しいものであってほしいと願う心の集積だと言える。
庭には、美を求められるが、それは芸術でなく、石や木や花を使って、この世界が美しくあってほしいという人間の願いなのだと思う。その切片を庭という場所に感じたいのではないだろうか。このように考えると現代の庭は知らぬままに、随分形式化され、形骸化してきたもののように思える。私たちは、いつしか庭を「モノ」として捉え、時に「商品」とし、「芸術」とし、庭に流れる私たち人間の本来の心を無視してきたのではないだろうか。このことは、庭を作ることを生業にした庭師の問題であり、庭が人々から遠ざかり、ただ、ありがたく鑑賞する対象となってしまった要因かもしれない。庭のこめられていた様々な喜びや願い、祈り、畏れが消え去り、カタチだけが残っているとも言える。そして、このことは、和歌の世界で起こったように月を見ていないのに月の歌を詠み、花を見ていないのに花の歌を詠む行為に似ている。
※7 小林秀雄 小林秀雄全21 「美を求める心」 新潮社 251頁
平な土地から夢が生まれた
庭は、洋の東西を問わず、平な囲われた土地に生まれ、人間の主体的な営みで、好ましい自然を作ることを目的としてきたことを見てきた。そして、その庭の中は、古い人間の思考で作られ、この世界を愛しく眺めたい美を求める心と精霊たちとの出会いの場所であり、人々が夢みる場所であると言える。世界中の人々が、庭を手放さない理由はここにあると思う。
庭は、グリーンと呼ばれるマテリアルな存在ではない。庭だけが、「ガーデニングとING」を常に持つように、厄介で可変で、自分で作ることのできる場所なのだ。その姿はまさに「美しい世界を求め続ける生命の気持ち」そのものと言える。そして、世界に目を向ければ、座敷がなくても消滅することのない「自立的」場所だったのだと言える。
未開部族と呼ばれる無文字文化の人々が、自分たちの住む森について驚くべき知識を持っていることは現代の民俗学者が解き明かしている。当然、サピエンスとして彼らの脳は私たちと何ら変わりない。最近成り上がった「現代人」としての思考が、庭を見えなくしているだけなのだ。庭の形式や姿は、文明と共に変遷するが、全ての庭に込められているのは、未開人だった頃の私たちの古い記憶なのだ。そして、今でもその記憶によって世界各国で庭は作られ続けているのではないか。庭を失った時私たちは、その記憶を失うことになる。
用と美
さて、日本の庭に戻ろう。座敷と言う主人を失って悲嘆に暮れて、出発したが、本来庭は自立的存在であることも分かった。
先に記したように日本では、屋戸と島が生き残って庭となっている。そして、島と屋戸は、別種の性格を持つため、現代的に言えば、外構と庭に区切られている。この二つの区切りは幻想ではないのかという疑問である。島の発達によって、抽象化し非日常化しすぎたために分断したに過ぎないのではないかという推論である。現代のリビングを中心にした庭空間は、「普段の暮らし」を支えることが主目的になったと言える。そのような場所で抽象化は必要なのだろうか。庭もまた、普段着の庭に着替えることが求められているのではないだろうか。
そのヒントになる庭が日本には残されている。日本庭園の中で異彩を放つ茶庭だ。
茶庭という言葉は、意外なことに幕末以降に使われた言葉で、茶人は、これを「露地」と頑なに呼ぶ。簡単に茶庭と呼ばれるものを説明すると、茶庭は、茶室に至る経路として、寄付、待合から始まり、中門、腰掛け待合、路地、そして茶室を含む空間を指す。この中に、日本庭園の三種の神器と言われる「蹲、灯籠、飛び石」がある。この三つを作れば、日本庭園風に見えるという意味だが、茶庭の歴史は、それほど深くはない。有名な千利休以降のものであり、寺社仏閣でしか使われていなかった灯籠を庭に入れたのもこの時以降となる。蹲は、茶室に入る前に身を清める場所であり、「洗面所」は言い過ぎかもしれないが、機能的にはそのような性質を持つ。
この庭には、二つの点で特異な性質を持つ。一つは、茶会を催すための「使う庭」であること。当然、鑑賞もするが、使うことを重視して作られている。次に、茶庭は「等身大」で作られていることだ。日本の庭が、まるで大自然を網で掬い取り、小さな籠に入れるように縮景されているのに対し、茶庭は、実物大で作られている。茶道が発達したのは、大阪の堺だが、あのような街中で広い庭を作れる訳も無いが、茶庭は「市中の山居」を目指している。市中の山居と言うのは、簡単に説明すれば、街中でいるのに、山の中で暮らしているような世界観を指す。かなり、特異な作りなのである。この二つの特徴を聞いて、多くの方が胸に手をやるのではないだろうか。便利な住宅街に一戸建ての家を建てる。駅からも近い。ショッピングモールもあるし、学校へも便利だ。しかし、自宅に向かうとそこは雑木林に囲まれた別世界であり、しかも、庭では色々用事もなさなければならない。茶庭は現代人の私たちと同じように「夢みる」矛盾を内包しているのだ。現代の私たちの家や庭に対する憧れに実に似ていることに驚かれると思う。
茶庭は、枯山水式庭園も縮景式庭園も否定し、抽象化をやめ、実物大の自然風景を取り入れ、茶室へ向かう道を作った。そのため通路までも露地として取り込んだ庭なのだ。例えば、役石という言葉が茶庭にはある。役石とは目的を持った石ことで、蹲を構成する石は、ただ、意味なく並べられた石ではなく、湯桶を置く石、手燭を置く石と決められている。冬の茶会で暖かい湯を入れた桶と夜の茶会で灯りを置く石といえばご理解いただけると思う。また、一見、ランダムに並ぶ飛石も、(流派によって異なるが)右足から歩くか。左足から歩くか。ということを考え、据えられている。その他にも、亭主が客人をお迎えし、挨拶する石、これは通常やや大きめで立ちやすい石を使うが、このように様々な役石が置かれている。
私が、初めて茶庭の手入れを専門でされている茶庭師にご指導頂き、学ばせていただいた時、その意味ある合理性に心底驚嘆し、ひどく感動をしたことを憶えている。つまり、露地と呼ばれる茶庭は、実際に使いながら、市中の山居という世界観に覆われた世界を実現している。これを一般には「用の美」と言われるが、ここでは「用と美」二つの概念を融合させた手法として理解するべきだと思う。
現在、庭と呼ばれる場所は、過去、屋戸や大庭を含んだ使われる場所であったことを冒頭示した。現代で言えば、駐車場や駐輪場、物置、立水栓などがそれにあたる。しかし、いつしか私たちは島だけを取り出して、庭と考えるようになったが、露地の世界では、旧来の庭を否定し、目的に向かう路をも含めて一つの世界観を作っているのだ。
もしこの考えを、現代の家に援用するなら外構と庭を分離せず、家をも含めた「全体性」をデザインし等身大の世界を作ることになる。旧来の日本の庭では、物干しや物置、水栓や畑などが除外されてきたが、露地では、雪隠と言われるトイレ、腰掛け待合と言われるベンチ、塵穴というゴミ箱までも庭に取り入れられている。
そうであるならば、私たちが、友人と楽しむBBQをするコンロ、ピザ釜、また、昼寝をするハンモック、子供たちの砂場、布団干しや遊具、そして食育のための家庭菜園など、それらを庭に迎い入れ、その「用」だけでなく庭的「美」を持って再構成しなければならない。家、通路、畑・菜園、庭、駐車場、物置、立水栓、それら全てを含む新しい庭。そのあるべき姿が茶庭を通して垣間見られるのではないだろうか。私たちは、もう一度、庭を解体し、茶人たちのように自分たちが求める姿を追い求めなくてはならない。そのことが、豊かさや美しさ、幸福というものを求める心=庭に埋められている心、につながっていくのではないかと思う。
さて、平成は、私たちから古き概念を打ち壊し、古き良きものを選ばしてくれる「チャンスの時代」でもあったのだ。新しい庭が目覚める時だったのだ。
最後に自身の、そして我々への警句として、ジャック・ブロスの言葉を記したいと思う。
「このようにキリスト教会が勝利をおさめてからというもの、崇めることの許される樹はただ一つ、贖い主がその上で死んだあの四角い木だけになってしまった。他の崇拝はすべて禁じられ、それらを一掃しようとして福音伝道者たちの払った熱意については周知の通りである。
多様性、相互補完性に根ざし、複合的で互いに関連し合った宇宙論―古代の「多神教」がそうであるーに代わって、教権的、不寛容で二元論的な一神教がその跡を引き継ぐことになった。善悪の区別という名のもと、旧い精神状態に対する反動から、魂は肉体から切りされ、人間は自然から隔てられた。当然神につながるのは魂であるから、自然も肉体も必然的にそこから排斥されたのである。自然や肉体は人を誘惑に駆りたてるものにすぎず、エデンの園追放に責任を負うべきかつての知恵の樹の蛇のように、悪魔の手先以外にはなりえなかったのだ。(中略)
こうして生きとし生けるもの同士の交感の上に立脚していた生命のバランスは崩壊し、その最終的な影響が今日人類の上にふりかかっている。かつて開放的だった人類は次第に自らの内に同じこもり、その頑な人間中心主義のため、もはや人類以外の存在は物としか映らなくなってしまった。自然全体が価値を下げることになったのである。かつて自然の中では、すべてものが何かのしるしであった。自然それ自身がある意味をもち、人はそれぞれ心の内でその意味を感じとっていた。しかし人間はそれを見失ってしまったがゆえに、今日自然を破壊し、またそうすることによって自ずから裁かれているのである。」 ※8
庭に息づく人々の心を考えると、庭は決してモノでも器でもなく、商品でもなく一人一人の心のカタチだと言え、その心から夢を取り出し、カタチを与えることが、庭という場所であろうと信じている。だから、庭は面白いのだ。分割できない私たちの心が眠っているのだ。
※8 ジャック・ブロス著 「世界樹木神話」 八坂書房 448頁
【参照文献】
重森三玲著 「枯山水」 中央公論新社
重森三玲・重森完途著 日本庭園史大系 上古・日本庭園源流1 社会思想社
宮本常一著 「日本人の住まい―生きる場のかたちとその変遷」 百の知恵双書
藤森照信著 「フジモリ式建築入門」 筑摩書房
小林秀雄著 小林秀雄全作品27・28「本居宣長」 新潮社
ペネロビ・ボブハウス著 高山宏日本版監修 「世界の庭園歴史図鑑」 原書房
中山理著 「イギリス庭園の文化史」 大修館書店
森 蘊著 「「作庭記」の世界」 日本出版放送協会
関根正雄翻訳 「創世記」 岩波文庫
W・J・オング著 「声の文化と文字の文化」 藤原書店
企画・編集 株式会社 創園 「創園」 株式会社ミサワホーム
中沢新一著 「精霊の王」 講談社
中沢新一著 「カイエソバージュⅠーⅤ」 講談社
藤森照信著 「茶室学」 六耀社
神津朝夫著 「茶の湯と日本文化」
飯島照仁著 「ここから学ぶ 茶室と露地」 淡交社
岡倉覚三著 「茶の本」 岩波文庫
投稿日:2021/08/18